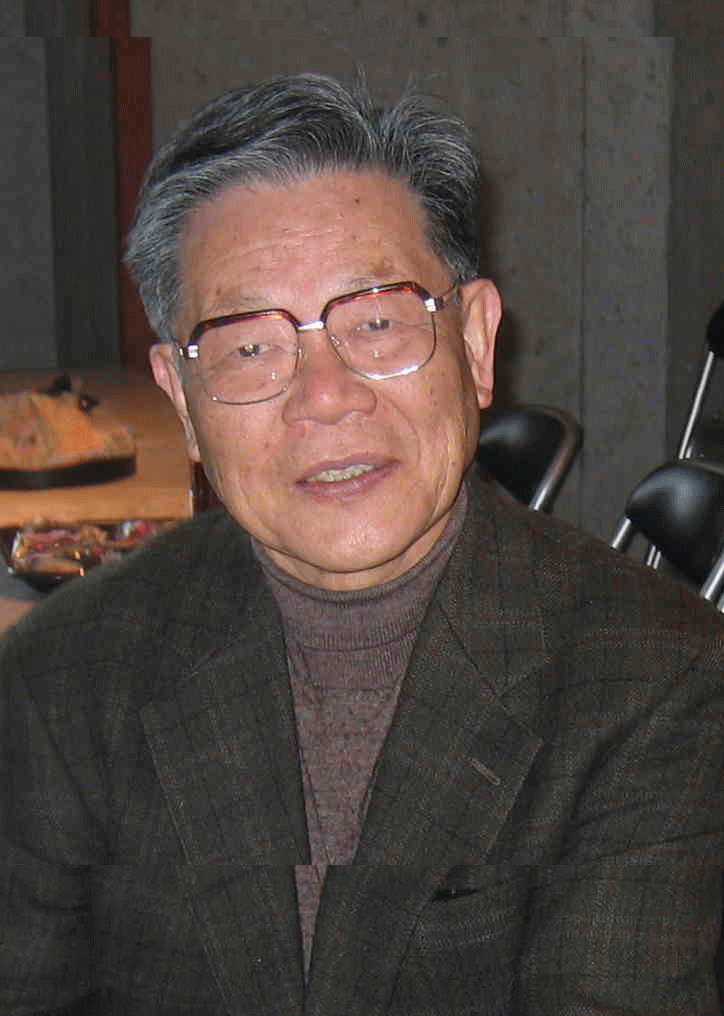
水と葡萄酒
-ヨハネによる福音書2:1~11を中心として-
2007・4・29 ロゴス教会における信徒証言
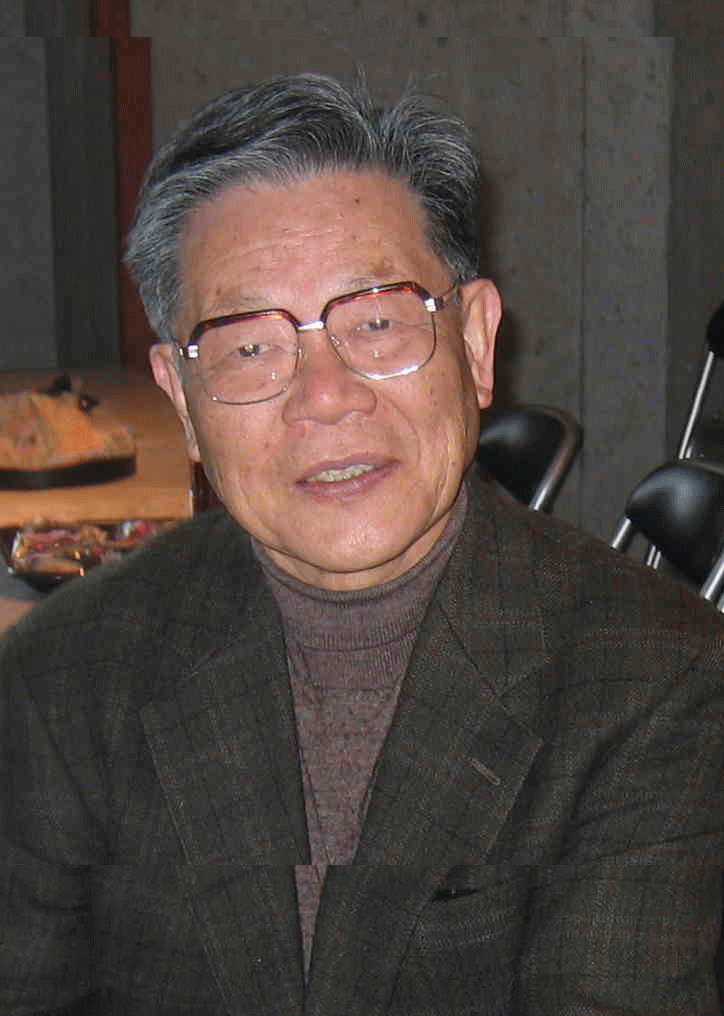
中野 光
Ⅰ.聖書に私を近づけた人
このような機会を与えていただいた時、どういう内容を語ることが私にとってふさわしいのかと考えました。はじめは「聖書を読む」とでも題して、私にとって聖書とは何であったのか、それをどう読んできたのだろうか、を振り返る機会にしようか、と思いました。しかし、そうなると限られた時間ではとても難しく、結局は散漫なものになってしまうだろうと思いました。もっと内容をしぼってみようと思い直したのでした。そこでご案内のような「水と葡萄酒」という主題でヨハネによる福音書第2章・「カナの婚礼」に基づいてお話を聴いていただこうと思いました。
その前にお断りしておかなければならない事があります。それは私は聖書をところどころ、しかもごく浅くしか理解してこなかった、ということです。そんな私を聖書に近づけてくださった人が二人ありました。一人はずっと昔、江戸時代の初期の儒学者、伊藤仁斎(1627~1705)という人です。もう一人は現在もご健在で、前立教学院々長・新約聖書の研究では碩学と申し上げてよい速水敏彦さん(1927~)です。
伊藤仁斎は京都の堀川のほとりに古義堂という私塾を開設し、儒学の研究と教育とを結びつけた個性的な学者でした。当時の儒学といえば幕府が公認した朱子学とそれとは異なった立場の陽明学という二つの学派に分かれていたのですが、仁斎はそのいずれにも属さず古義をたずねて正義を探求するというのが彼の立場でした。その教育方針も当時としては個性的でした。大半の私塾に学ぶものは武士の子弟のみでしたが、仁斎の塾では庶民(町衆)も出席できました。雰囲気も自由闊達で、各人一名一果を持ちより胡坐をかいてすわり「生活を脚注にして」テクストを読めとすすめました。
「生活を脚注にする」とは、偉い人・権威者の学説をうのみにしたり、いわば受け売りをするのではなく、自分の目で見たこと・自分の耳で聞いたこと・自分の脳みそで考えたことを、つまり自らの生活経験・実証的事実にもとづいてテクスト(四書五経などの古典)を読み解くことを意味しました。
仁斎は自分の学説を弟子たちに押し付けることをしないで、他人の意見をじっくりと聴き、たとえ間違った見解でも噛んで含めるように語ったといいます。彼の述実や弟子たちの評価などを知りますと私には仁斎と山本三和人先生とが重なって浮かんでまいります。聖書もまた生活を脚注にして読んでいいのだということになれば私にとってやや気楽になりました。
私を聖書に近づけてくださったもう一人の方は速水俊彦先生です。先生は私の立教大学在職中の同僚で尊敬していた方でした。私が立教を去ってからも親しくしてくださり、手元には二冊の御著書があります。『新約聖書―私のアングル』という書物は1987年の書物ですが、そこでは、
速水先生は聖書について
「順序だてて読む必要はない。――どこから読んでもいい」「わからないところはとばして読んでもよい」「イエス様について信じられないことが書いてあったらあまりこだわる必要はない。時にはどうでもいいと思ってもかまわない――」など、こんなことを聖公会の司祭・キリスト教主義大学の教授が書いてもいいのか――と思ったことがしばしばありました。また先生とお付きあいをしていて、私のほうが真面目だと思ったことがよくありました。この速水先生もまた現代における伊藤仁斎的人物かと思ってきました。
Ⅱ.マリアとイエスとの会話
さて、ヨハネの福音書の第2章第1節から11節の短い部分、これは有名なカナの婚礼にイエスとマリアが招かれたときの話です。私はこの箇所についてもう40年も前のことになりますが、二つの疑問を感じました。
第一は、お祝いの会場でマリアが息子のイエスに「ねえイエス、お祝いの葡萄酒がないのよ。どうしたらいい?」とたずねます。その時聖書によりますと、イエスは「婦人よ、あなたはどうして私にそんなことを聞くの?ぼくの出番じゃないよ。そんなこと」――これは私が聖書を読んだときのイメ-ジですが。――(たぶん二人のこの会話はしらけた雰囲気だったように私には想像されます)そこでマリアは会話の相手を変えて「皆さんこの人は相談すれば何かと力になってくれる人です。ですからあの人に頼んでちょうだい」と、周りの人に言ったようですね。ですからイエスの相手は今度は母マリア一人ではなく、人々になるわけです。イエスはそこにあった六つの水がめを指して「あの水がめに水を満たしなさい。」といわれた、こう読み取れますね。
そこで、40年ほど前に私が疑問に思ったのは、イエスがマリアに対してなぜ「婦人よ」と言って「お母さん」と言わなかったのだろうかということでした。私はあまり細かいことにこだわる性格ではないと自分では思っているのですが、念のためにクリスチャンの友人に聞いてみたことがありましたが答えは返ってきませんでした。そこで当時私の書棚にあった「矢内原忠雄全集」(岩波)の「聖書講義」の巻をひもといてみましたところ、矢内原さんは当該箇所に次の様なコメントを書いておられました。(私の記憶によれば)「イエスがここでマリアを母と呼ばずに婦人と言ったのは、家族内の母と子との関係ではなく、会衆の中の人と人との関係を区別されたと考えられる。」
私はこのコメントに納得しました。神の前にすべての人間は親子・夫婦の関係をこえて平等であるのですから。
なお、私は最近英語とドイツ語の聖書、それに偶然ですが私が戦後間もない青年時代に持っていた古い聖書を手にすることができました。そこではイエスの発言はやはり“マザ-”ではなくて“ウ-マン”、”ムッタ-“ではなく”ヴァイブ“でした。古い聖書では”婦人よ“ではなく”女よ“でした。しかし現代の日本ではこのような代名詞にこだわる必要はないのではないか、というのが私の結論です。
ちなみにギデオンの新しい聖書では“お母さん”となっており、松本さんからお借りした山浦玄嗣さんのケセン語訳新約聖書では“おかさまんす”と訳されています。暫らくの間生き生きとしたその箇所をお聴きください。
Ⅲ.水から葡萄酒へ
若い時代に疑問に思い、こだわってきた第2のこと、すなわち水がどうして葡萄酒になったのか、という問題です。
イエスは水H2Oを魔術師のように葡萄酒というアルコ-ルに変えたのでしょうか。「奇跡的な栄光」であるとするなら第2章1節~11節をどう読んだらいいのか。もし私に数理哲学史的教養があったら六つの水がめの6に問題を解く鍵が含まれていたのではないか、ということも考えましたがそれは未だに分かりません.
考えられることは昔も今も“水”とはこの地球上に生きるものにとって生命の源泉であり、清純なるもののシンボルであるということです。聖書の中で“水”がどういう文脈でどう使われているか、という問題も興味深い問いだと思います。また”葡萄酒“についてもそれは人間にとって単なる癒しと喜びの美味なる祝い酒ではなく、人間の救いのために流されたキリストの血、神が神と人とを結び付けてくださったことを象徴するもの、さらに言えば人間の生きるうえでのエネルギ-源ともいえましょう。聖餐式のパンと葡萄酒に思いをいたしてもそう思います。そんなことを考えますと水が葡萄酒に変わるというイエスによる「栄光」には深い意味が隠されていると考えざるを得ません。
そこで、私は伊藤仁斎流に私の「生活を脚注」にして、そのことを考えたいと思いました。話が個人的なレベルになることをお許しください。
私どもが結婚してから早くも半世紀が過ぎてしまったのですが、1950年代後半の日本は貧しい時代でした。私には結婚資金のたくわえもなく、友人の計らいで会費制による式を挙げ、お祝いをしてもらいました。新婚旅行というものもまだ一般的になってはおりませんでした。私たちは六畳一間で生活したのですが、日用品を母と一緒に新宿の荒物屋に買いに行ったのを思い出します。
多くの方々から祝福を受け、葡萄酒で乾杯してもらったのですが、現実は厳しくまさに「水」の状態から始まった、といえるように思います。今、私どもはそれでよかった、それがよかったと思っています。私たちにとっての葡萄酒は「水」から始まった生活の中で「葡萄酒」に恵まれていったように思われます。それは神の恵みと導きによるものと思っています。
しかし、2007年のいま、私たちは半世紀前とは大きく変わってしまった歴史のただ中に生かされています。60年代以降、私たちは職業柄しばしば結婚式で媒酌の役目をする機会を与えられてきましたが、年を経るごとに結婚式は派手になり、その費用は膨らんできました。戦後世代の私たちは親に負担をかけまいという心積もりをしたものですが、今では親が負担することがむしろ当たり前のようになって来ました。
さらにここ十年ぐらい、結婚式の全体が司会者を始め海外への新婚旅行を含めてワン・セットの商品として考える、という現実に遭遇するようになりました。青年も子どもも「与えられるものの過剰、自ら獲得するものの過少」のゆえに人間として体験すべき生活が貧しくなっています。いやほかならぬ私ども自身がそのような時流の中にあって真実の姿を見失っているのではないでしょうか。
そうであるからこそ、ヨハネによる福音書の内容は私たちにとって輝きをもって真実を示しているのではないでしょうか。