軍都廣島から平和都市ヒロシマへ
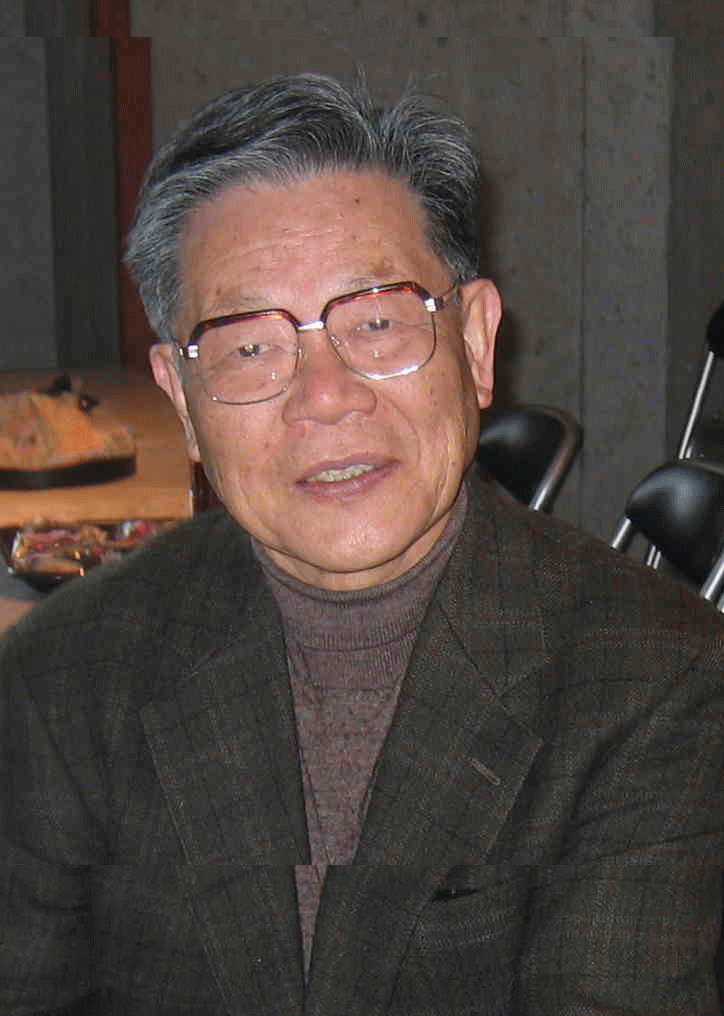
中野 光
戦中から戦後へ(2)
軍都廣島から平和都市ヒロシマへ
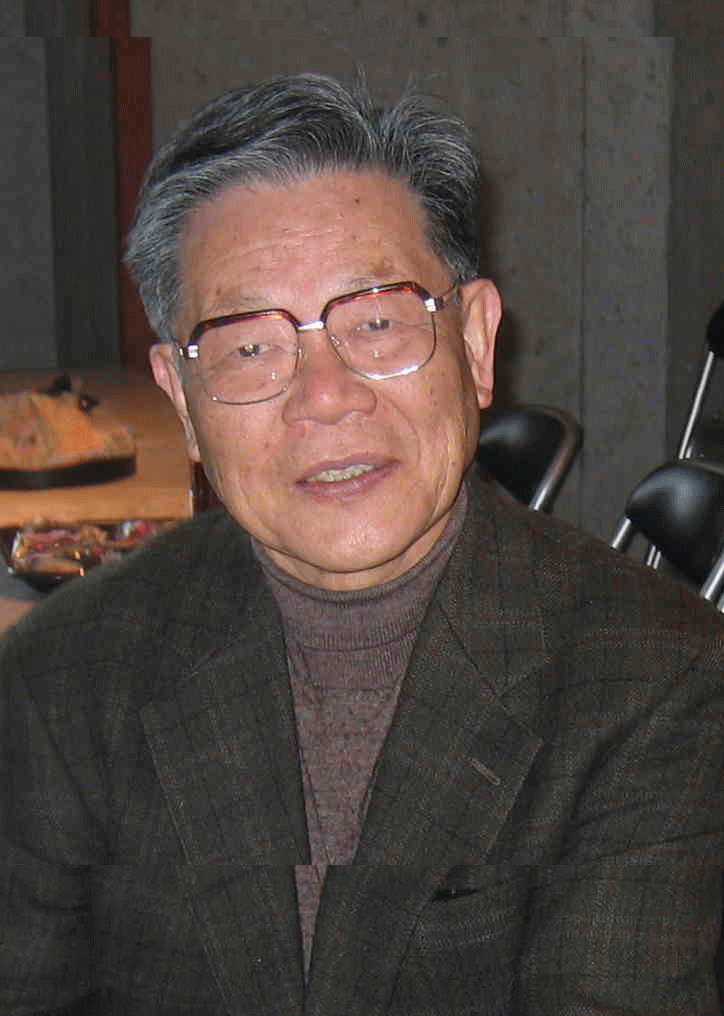
中野 光
主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。
彼らは剣を打ち直して鋤となし、槍を打ち直して鎌とする。
国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。(イザヤ書2章4節)
1.軍都廣島の最後
敗戦から10日ほどたった8月24日の昼下がり、私の乗った復員列車は石炭を積んだ無蓋車で、その石炭の上に乗せられたのだった。落ちないように体を縄で縛っていたかと思う。山口県の防府から発って最初に停車したのは戦災を受けて焼け野原になった徳山だった。文字どおりの焼け野原、しかし焼け跡には土蔵や鉄筋コンクリ−トの建物などが残り、多くの人々が跡かたづけのために立ち働いていた。
列車が広島に着いたのは薄暮時、私はそこで一瞬息が詰まる思いだった。ホ−ムの屋根はぐにゃぐにゃに曲がり、鉄骨はよじれ、市街には人が見当たらなかった。見渡しても視界をさえぎるものすらない、不気味な死の町だった。ところどころに白い煙だけが立ちのぼっていた。この様相は後に著名な作家になった期友の早坂暁が作品『夢千代日記』などに詳しく描いている。列車がゴトリと動くまでの時間はかなり長かった。五ヶ月前までの軍都廣島――かつて、ここには戦争の最高司令部である大本営が置かれていたこと、廣島の宇品港からはアジアの各地に軍隊が送り出されていたことなどにより軍都と呼ばれていた――のなんと変わり果てたことか。
しかし、その時私たちには原子爆弾について何も知らされてはいなかった。
2.ヒロシマ・ナガサキをよみがえらせたもの
原爆投下とそれがもたらした惨状については、占領軍の厳しい言論統制によって、私をふくむ多くの日本人は真実を知るすべはなかった。私にとって戦後早い時期に、被爆の惨状を知らせてくれたのは永井隆、イサム・ノグチ、長田新の三人であった。
永井は長崎の原爆で妻を失い、自ら白血病に苦しみつつ遺した「ロザリオの鎖」「この子を残して」等が多くの人々に原爆の悲惨さを知らせた。イサム・ノグチは詩人の野口米次郎を父にもつ国際的な彫刻家、広島の平和公園にかかる橋のデザイナ−。
そして長田新は戦前からスイスの教育者ペスタロッチの研究で知られた教育学者。
1951年、被爆した子どもたちの作文を集め、『原爆の子――少年少女の訴え』と題して岩波書店から出版した。
この三人の仕事をつらぬいた思想は「復讐の連鎖」を断ち切って平和の思想を日本だけでなく世界に広げたということだった。
3.ヒロシマで旧友と再会
海軍兵学校時代、もっとも親しかったのは名越謙蔵だった。彼は鹿児島県種子島の出身、私とは名簿の上で「ナカノ」と「ナゴシ」とつながっていたので、自習室の机は隣同士だったし、ベッドでは上段が名越下段が私だった。戦後も3年間ほど文通が続いたが彼が旧制七校に入学し、私が高等師範へ入って以後文通は途絶えた。
たしか1960年代の終わりごろ、私は偶然にも『ぼく生きたかった』と題する一冊の本を求めて読んだ。いわゆる被爆二世の名越文樹君という幼な子の白血病との闘病と母親の看護記録だった。ところが読み進めていくうちにこの文樹君の父親があの名越謙蔵であることがわかって驚いた。この本の執筆者は夫人の操さんで8月6日爆心地に近いところで被爆されたのだった。二人は戦後の平和運動の中で結ばれたという。私は『ぼく生きたかった』を読んで沈痛な想いにうちひしがれた。さっそく手紙を書こうと思ったが、文通が途絶えて二十年もたっていることと海兵のクラス会がまぢかに予定されていたのでペンを執らずにいた。クラス会に私は金沢から行ったが、名越は欠席だった。幹事宛に寄せられた彼からの書簡には『私を海兵にいざなった教育と思想はいまの自分にとってたたかいの対象であり、過去をなつかしむような機会はつくりたくはない。』という“断り状”だった。
名越との再会はそれから20年たった1980年代の後半、廣島で平和教育の国際シンポジュウムが開かれたときだった。三度目は1991年の6月、中央大学の学生と廣島旅行をして爆心地に近い元安川の川底で”原爆瓦“を拾った後のことだった。それから数年たって私は彼の訃報に接した。ヒロシマを想うとき、彼の姿が私の脳裏にうかんでくる。