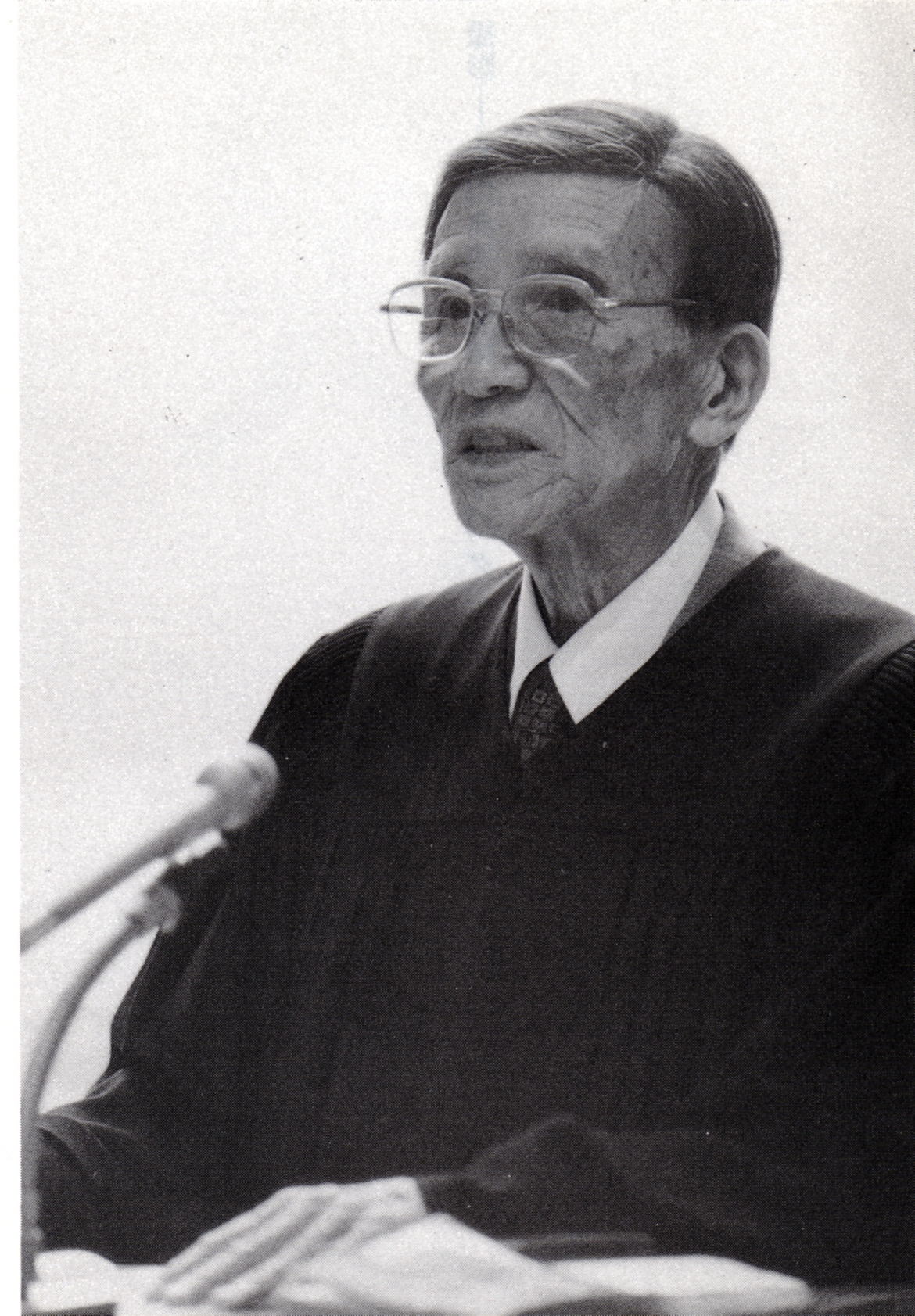
女と男
(ろばのみみ7 1963.5.17)
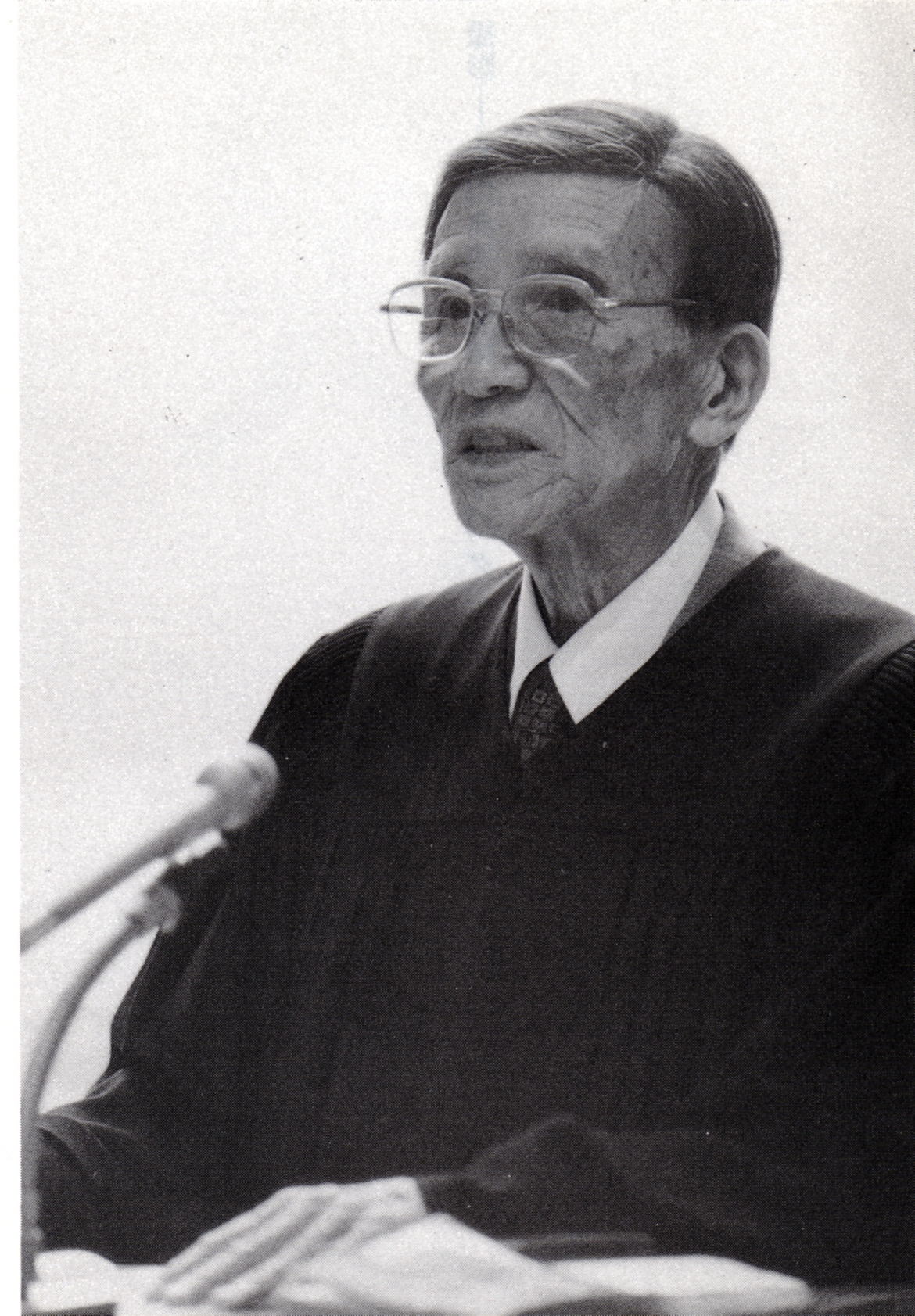
山本三和人
”「泣いた女が馬鹿なのか」 「だました男が悪いのか」”
これは、「東京ブルース」という歌の冒頭の詞です。むろん、女性の立場からうたったものです。これによりますと女が善良で、弱くて、男にだまされて泣いて歌ったものです。男は悪くて、非情で、弱い女を泣かせてばかりいるみたいです。
Nという女性歌手がちょっとハスキーな声で歌っているのがこの歌がどこからともなく聞こえてくると、男としては、「何を勝手なこといっている」と、いいたい気持ちになります。
しかし、永い歴史の中で男が女性に与えてきた不当な取り扱いのことを考えれば、こんな歌の二つや三つくらい作られて歌われたからといって、別にどうということはない、と思います。
私たちが子どものときに聞かされて、今でもよく覚えている『舌切雀』の話の中では、男は親切で善良な人間に性格づけられていますが、反対に女は非情で、残酷で、欲張りとして語られています。
東洋では、伝統的に女性は一個の主体性を持った人間としての取り扱いを受けませんでした。「女のくせに!」といって、その発言がしりぞけられ、社会的な参加が認められませんでした。ことあるごとに、「女は三界に家なし」といわれ、「幼くして親に従い、嫁して夫に従い、老いては子に従うべし」と、生涯、服従を強いられ、「十方におわす諸仏も、女人をば成仏せしめ給うを得ず」と、きめつけられてきました。
これは東洋だけではなく、西洋でも同じでした。『パンドラの箱』という話の中では、パンドラという女の子の好奇心と虚栄心が大きな災禍を招くようになっていくのですが、その最初の犠牲者は、何も知らない善良なボーイ・フレンドのエピメシアスです。
また西洋の童話を読んでいると、たびたび悪や災厄の象徴として魔女が出てきますが、「魔男」は出てきません。反対に、天使はどれも男の姿をして出てくるのです。こういうことは、男と女の平等を説いているキリスト教の聖書でさえ例外ではありませんでした。
旧約聖書の『創世記』の初めの話は、神さまに造られた最初の人間はアダムという男であり、女はその孤独を慰め、男の不自由をなくし、男の仕事を助けるためにーつまり、男の幸福達成の手段として、そのアバラ骨の一本でつくられた、と書いてあります。言い換えれば、「男は神のために存在し、女は男のために生きるようにつくられた」と記してあるのです。どうもここでも女性の主体性は認められていないようです。
ローマ帝国の暴君といわれたネロは、あるとき数百人の学者を宮廷に集めて、「女に魂があるか」という問題を討議させたそうですが、永い熱心な討議の後で、衆議一決した結論は、「女には魂がない」ということだったそうです。これだけではなく、聖書はさらに女を悪者に仕立て上げます。
男の喉の部分にある突起を、「アダムズアップル」といいます。創世の初め、エデンの園に住まわせたアダムとイブの二人に対し、神さまは<自由と禁令>を一つづつ与えました。
「あなたは園のどの木からでも心のままに取って食べてよろしい」ーこれがその自由です。
「しかし善悪を知る木からは取って食べてはならない。それを取って食べると、きっと死ぬであろう」−これがその禁令です。
アダムは神を信じ、その戒めを重んじていましたから、神さまのことばの枠の中での自由に満足していました。しかしイブは、蛇<虚栄という意味>にそそのかされ、禁断の木の実を取って食べてしまいました。
それがよほどおいしかったとみえ、イブは夫のアダムにもその一つを差し出して、食べるようにすすめました。アダムはもちろん、「いやだ」といったのですが、イブは、「あなたは私と神さまとどっちが大事なの」といって、夫の愛を試しました。
アダムは心から妻を愛していましたから、結局はイブのことばに従って、とうとう木の実を一つほおばってしまいました。
そのとき、アダムの背後から、神さまが、「アダム!」と呼びかけました。驚いたアダムは、口に入れた木の実を喉にひっかけてしまったのです。その木の実が、今でも全ての男の喉のところにある突起物となって残っているので、これを「アダムズアップル」というのです。
この話のように考えますと、男の喉の突起物は、男の小心さと良心の健在を示すことになり、女の喉のなめらかさは、女の大胆さ、あるいはふてぶてしさを表す証拠だ、ということになります。
女はこのように悪であり、罪深いものでありますから、「子を産む苦しみが与えられ」、一方では、「会堂の中にて黙すべし」といって、永い間、公衆の面前での発言が許されませんでした。とはいえ、「たとえば女性には、室内で帽子をとらなくても良いという特権がる。あれは女性が優遇され、特権を与えられている証拠ではないか」という人がいるかも知れません。
そうではないのです。あれはパウロの、「女は教会の中において帽子をかぶるべし」ということばからきたもので、「かぶっても良い」というのではなく、「かぶらなければならない」という意味です。もっとはっきりいってしまえば、「女の髪は汚れているから、人の集まる場所ではそれを帽子でおおいなさい」という意味です。つまり、室内で女の人が帽子をかぶっているのは、自分の醜さと、罪を認めていることになるのです。
こうした男尊女卑の考え方に終止符を打ったのは、なんといってもイエス・キリストです。パウロは、「男は女より出でずして女は男より出でたり」といったすぐ後で、「されどキリスト・イエスにおいてはユダヤ人もギリシャ人もなく、自由人も奴隷もなく、男も女もなく、みなイエス・キリストにおいては同じ人間である」といったのです。
旧い歴史の終わりを意味するキリストの十字架上の死に立ち会った最後の人間は、女性のマリアであり、新しい歴史の発端を意味するキリストの復活に遭遇し、そのよみがえりをいち早く伝えた最初の人間もまた、女性のマリアであったことは、周知の事実です。
また、それまでの英雄主義的小説が影をひそめ、キリスト教文学があらわれてくると、女性が男性に代わって物語の中心的位置につきはじめました。
たとえば、ゲーテの『神曲』に出てくるダンテの霊はピアトリスの霊に導かれて天界に上がり、ファウストは、「とこしえに女性なるものに依って」いと高きところへ引き上げられ、ドストエフスキーの『罪と罰』では、罪を犯したラスコリニコフが、夜の女ソーニャの励ましと口ぞえで更生の道につくのです。
日本においてもかつて、キリシタン禁制が解かれて外国の宣教師が長崎に教会の建設をはじめたとき、「マリア様の御座所はどちらですか」と尋ねて行った最初の日本人は、名前も定かでない三人の女性であったと伝えられています。
まことにイエス・キリストこそ女性の解放者、「レディズ・ファースト」の真の実行者だといえると思います。
私は聖書を紐解くたびに、いつもそのことに思いを寄せているのです。