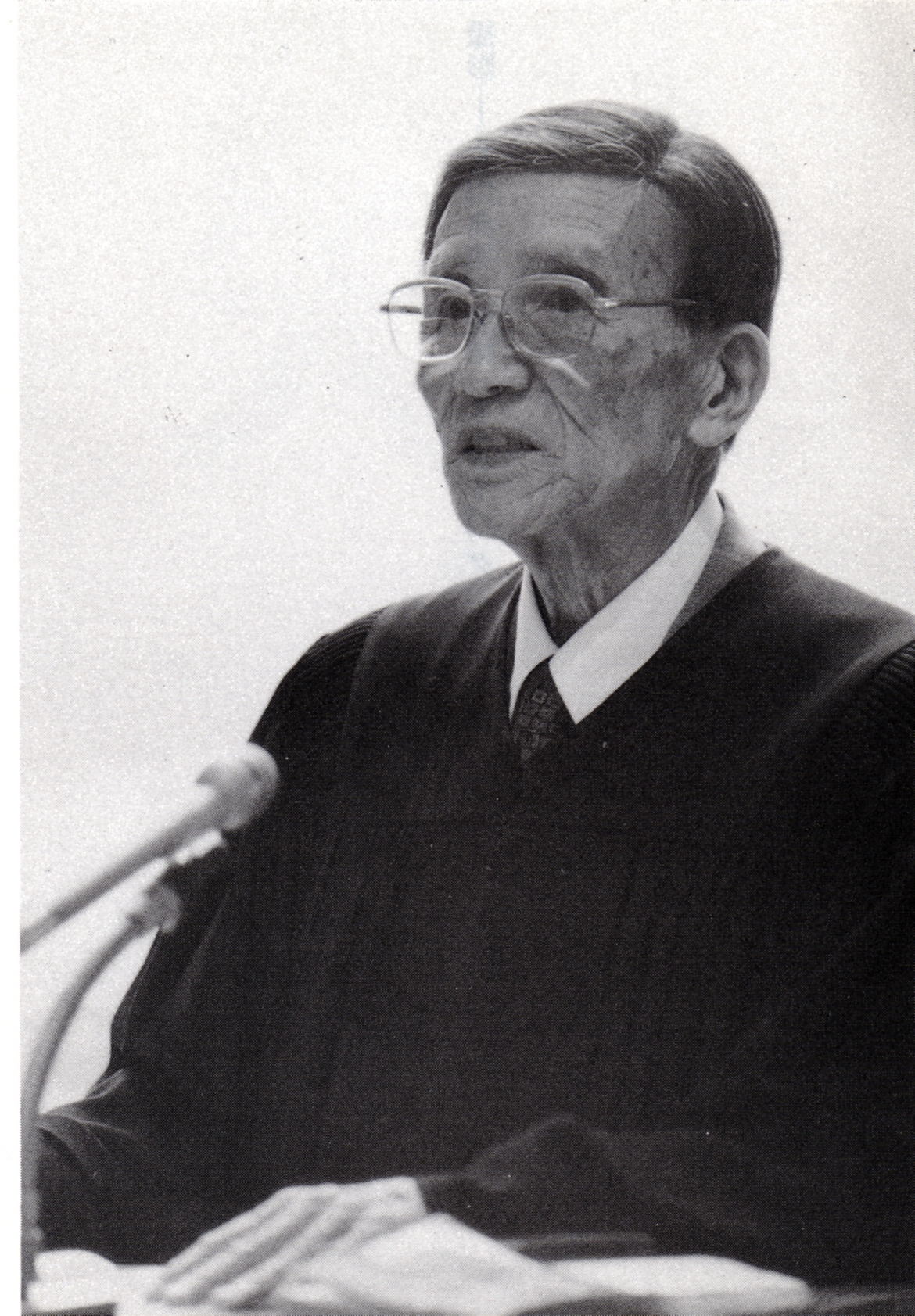
ほんとうの道
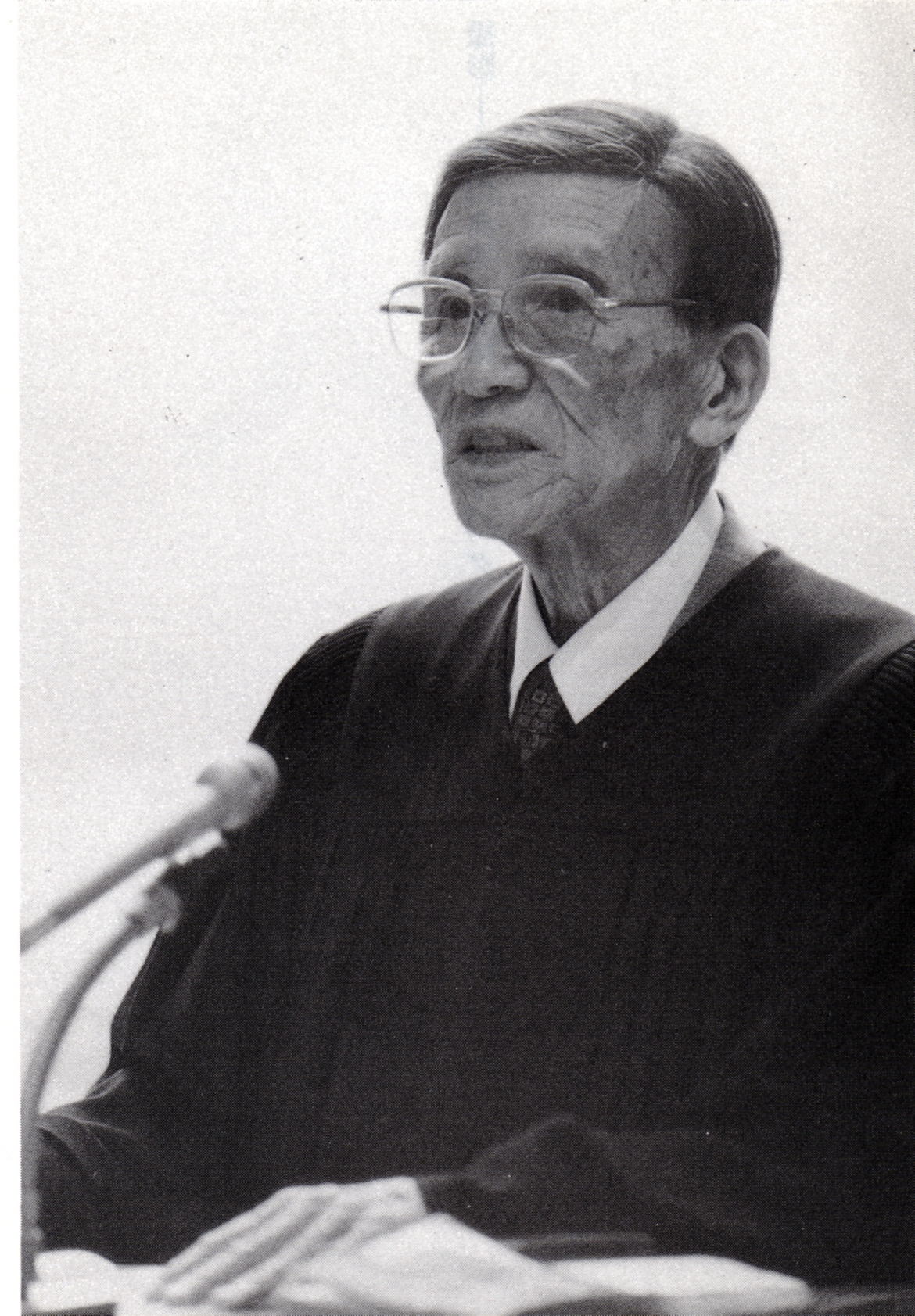
山本三和人
ほんとうの道は、一本の綱の上に通じている。その綱は空中に張られているのではなく、地面のすぐ上に張られてい る。渡って歩くためのものであるよりも、人をつまずかせるためのものであるらしい。『実存と人生』フランツ・カフカ
これはフランツ・カフカがその著『実存と人生』の巻頭で述べていることばです。彼はユダヤ教徒であり、シオニストでありましたから、このことばをキリストについての直接的な証言とみなすことはできません。
しかし彼は、チェコスロバキアの市民権を持ち、そこに住んで西欧文化の母胎としてのキリストの福音に触れ、その影響を受けたと思われますから、このことばを、キリストについての間接的な証言、すなわちカフカの文学的な神奉仕のことばと受けとることは、必ずしも見当違いではありません。わたしなどはこのことばを初めて読んだときから今日まで、これはカフカの文学的証言であると思い続けてきました。
ご存知のようにキリストは、自分のことを「道」であると主張しました。しかし、どういう訳かこの「道」は当時の人々の目には隠されていて、これを見出した人は、彼をとりまく群衆の中にも、彼と起居飲食を共にした弟子たちの中にも、、またエルサレムの聖域で神に仕えていた宗教家たちの中にもいませんでした。
ですからエルサレムの都への途上、目の前に静かに横たわるエルサレムの姿が見えてくると、イエスは泣きながら言いました。 「もし、お前もこの日平和をもたらす道を知ってさえいたら・・・しかしそれはいまおまえの目に隠されている」
さらに、マタイによる福音書に目を向けますと、彼が一層悲しげに語ったことばが記されています。
「ああエルサレム、エルサレム、・・・・・・ちょうどめんどりが翼の下にそのひなを集めるように
わたしはおまえの子らを幾たび集めようとしたことであろう。それだのに、おまえたちは応じなかった」
「おまえの子らを集めようとしたが、おまえたちは応じなかった」ということばは、「子供たちを集めようとしたが、その上にある者が反対した」というように受けとれます。つまり、ここでのイエスの語りかけの相手は、「おまえ」ではなく「おまえたち」−。つまりエルサレムの町ではなく、町の指導者たちだったようです。市民の宗教的な教育と指導にあたっていた祭司だとか、教法師だとか律法学者たちであった、と思われます。
ですから、キリストにある「平和の道」は、エルサレムの一般市民はおろか、宗教の専門家たちの目にさえも隠されていたことが分かります。イエスが、「狐には穴がある、空の鳥には巣がある。しかし人の子(キリスト)には枕するところがない」と言ったのは「平和の道」としてのイエスの真相を知る人が一人もいないということに対する、人間イエスの孤独感を訴えるためであったと思います。
では、神の都エルサレムの指導者たちの目に「道」が隠されていたのはなぜでしょう。彼らがその「道」を渡って歩こうとはしないで、それにつまづき、それを危険視し、それを排除しょうとしたのは、どうしてなのでしょう。
それはおそらく、マルチン・ブーバーのいう神蝕の現象が起きていたからです。彼らの抱いていたとてつもない自尊心が、自分の落としたどす黒い影の中に「道」をかげらせて見えなくしていたのです。彼らは常に聖域に「道」を求め、雲の彼方、山の向こうに神を探して、その目をいつも「山辺に向けて」いましたから、地面すれすれに張られた綱の上に通じる道などは、彼らの目に入りませんでした。
それだけでなく、足もとの綱に足をとられたりしたために、それを危険視し、邪魔扱いにして排除しようとしたのです。実際、馬小屋のような不潔な場所で生まれたものを神とあがめたり、ナザレのような俗域と境を接する田舎で育ったものを救世主として迎えられることは、彼らの自尊心をはなはだしく傷つけることでだりありました。ですから彼らは、「ナザレからなんの良いものが出ようか」といって、キリストをしりぞけたのです。
預言者イザヤはすでにこのことを予見して次のように述べました。
「彼は主の前に若木のように、かわいた土から出る根のように育った。彼には、われわれの見るべき姿がなく、威 厳もなく、われわれの慕うべき美しさもない。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた」
さて、二千年の歳月を重ねて、今日の教会はどうでしょうか。かえりみて、イエスのみ心を悲しませるようなことはなにひとつ行われていない、と言い切ることができるでしょう。
悲しいことではありますが、わたしたち人間は、信徒も含めて、二千年前とあまり変わってはおりません。高いものを見ると尊敬し、あこがれたり、へつらったりしますが、低いものに接すると哀れんだり、さげすんだり、時には邪魔者扱いにもしかねません。人間はいまでも高いところに道を求め、足許の道には目もくれません。ですから、足許にある「ほんとうの道」は、いまでもわたしたちの目に隠されているのです。
ドストエフスキーが書いた『カラマゾフの兄弟』の中の「物語り」にでてくる「大審問官」は、カトリック教会を擬人化したもの、といわれます。その「大審問官」は、乞食のように、みすぼらしい姿で近づいてくるキリストに対して、それがキリストであることを知りながら、「なにしに来た、ここはお前の来るところではない」と、怒鳴って追い返してしまいます。
これは小説の中の話ですが、このようなことは、現実の社会の中でも行われています。有名な画家のゴッホは、若い時、見習い宣教師として、ベルギーの炭鉱街で伝道活動をしていました。しかし、炭塵にまみれた彼の姿が、教会の「品位」を傷つけたということによって、彼は解任の処分を受けました。
わたしたちは「信仰」や「聖域」や「気品」などを守るという理由で、自分でも気がつかないまま、あの「大審問官」と同じ過ちを犯しているかもしれません。すなわち、聖別のうちに差別意識を抱き、無意識のうちに貧しく、低い人々と共にいるイエスを、教会の外に閉めだしているのではないかと恐れます。
「ほんとうの道」は、「山の向こう」でも「雲の彼方」でも、エルサレムの神殿の至誠所のようなところでもなく、「地面のすぐ上に」張られた、「見栄えのしない綱の上」に通じていることを、固く心に留めて、その道を踏み外さないように信仰の生活を営んでゆきたい、と思います。